|
written in 2002.12.30
安価な野菜をはじめとして、割り箸からパソコンまで農産物、工業製品の多くが中国など海外で製造されている。しかし、価格の安さの代償に「安全性」を失っている事実も発覚している。飲食店やコンビニの弁当で使われる「割り箸」はいまや90%が中国産だが、工事現場の足場として使われていた竹を原料として、日本では認められていない薬品を使って製造処理されていることが指摘されて問題になった。また中国産の農産物が、基準を超えた農薬を使用していることがわかり、回収が相次いだことも記憶に新しい。
輸入品だけではなく、安心できるはずの国内生産品でも、産地偽装や異物混入などによって安全性が脅かされている。特に食品業界では、BSE(牛海綿状脳症)問題に限らず、バクテリアやウイルスなどの病原菌や毒物による危険性は常にあり、そのための検査は欠かせない。また、輸入された食品原材料の中に、国内では認可されていない遺伝子組み替え食品が混入しているという新しい危険性も生じている。
これらの問題が発覚した中には、食品メーカーが故意に不正をしたのではなく、メーカー自身も問題に気付かないまま商品を流通させてしまったケースも多い。
その背景には、あらゆるリスクに対する商品検査の方法と体制がまだ十分に整備されていない業界事情がある。
不良問題が発覚して、全国各地に流通した商品を回収することになれば、製造企業にとっては数億〜数十億円規模の損失になる。そこで商品を出荷する前に、様々なリスクに対応した“検査”を十分におこなっておくべきだという考え方がメーカー上層部の中でも浸透しはじめている。そこに着目すれば「商品検査」に関わる新しい市場が見てくる。
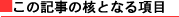
●安全性を気にする消費者の増加で成長する食品検査市場
●新たな食品検査サービス〜食品の遺伝子を検査
●米国における食肉流通のトレーサービリティの動向
●工業製品の検査代行サービスについての着目
●広がる検査ビジネスの民間委託による商機
●中古住宅評価制度が創出する住宅検査ビジネス

JNEWS LETTER 2002.12.30
※アクセスには正式登録後のID、PASSWORDが必要です。
|