


|
知財ビジネス化した農業と
子孫を残さないハイパー野菜 |
|
written in 2009/6/13
知的所有権が厳しく管理されている商材といえば、音楽、映画、パソコンソフトなど電子的な複製コピーができるものが知られているが、“複製が可能”という点では「植物」も同じである。一年草の植物は、春に発芽して夏頃に開花、秋には実を結ぶが、冬は越せずに枯れてしまう。しかしそこで残された種子を大切に保管して、翌年の春にまた蒔けば、昨年と同じ花が咲く。植物は種子による命の継承が行なわれているため、その種子を他人に広く譲り渡せば、同じ品種の花を全国各所で咲かせることができる。
しかし、人間が多額の研究費を投入して開発した新品種の植物で、そのような種子の無償配布をやられてしまうと、開発者の苦労が報われない。そこで工業技術と同様に、新品種の植物には、開発者の独占的な権利(育成者権)が認められている。特に商用となる農作物では、高付加価値に品種改良された種子が海外へ安易に流失して、自国の農業が深刻な被害を受けてしまうことの対策として、世界各国で植物特許(Plant Patent)による保護が行なわれているのだ。
日本では「種苗法」という法律がそれで、国が定めた要件を備えた植物の新品種育成に成功した者は、農林水産省に対して品種登録の出願ができるようになっている。その審査にクリアーして登録が認められると、独占的にその植物を商用利用できる権利(育成者権)が与えられる。
■品種登録ホームページ(農林水産省)
ただし、自然界に生育する植物すべてが権利登録できるわけではなく、これまでにない新品種であること、他の品種との区別ができること、その品種を安定して栽培できることなどが要件として挙げられている。そこでペットとして飼う犬や猫の交配と同じように、従来の品種と品種を掛け合わせて、鑑賞用として美しい花の新品種に改良したり、厳しい季節や風土にも適応して栽培しやすい新品種の野菜を開発することが、知財ビジネスとして昭和50年代から成立するようになった。
そして近年では新たに、バイオ燃料の原料となる植物の開発を促進する目的で、種苗法も改正されてきている。また、日本で登録品種に認められた植物は「新品種の保護に関する国際条約」に締結している世界の62か国でも権利が保護されるし、逆に他国で品種改良された植物の権利も、日本国内にまで効力が及んでいる。
では、どのように新品種の権利が守られているのかというと、「登録品種」あるいは「登録出願中の品種」とパッケージに明記されている種子や苗と、そこからの収穫物は、育成者(権利主)の許可なく増殖して譲渡することが法律で禁止されている。そのため、農家がブランド野菜の苗木を購入して栽培、収穫を終えてできた種子を、翌年に使ってまた栽培して販売したり、挿し木などによって繁殖することはできないルールになっている。
(知的財産ビジネス事例集一覧へ)
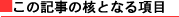
●知的権利で守られている植物特許の仕組み
●一代限りで子孫を残さないハイパー野菜の実態
●ハイパー野菜の流通構造
●食糧危機時代に備えた種子バンクのビジネスモデル
●環境貢献活動の裏にある独占的緑化ビジネス
●世界で展開される緑化ビジネスの仕組みと利権構造
●ヤワな日本人には太刀打ちできない一触即発の食糧危機
●水危機の到来に向けた「水を売るビジネス」の布石と死角

JNEWS LETTER 2009.6.13
※アクセスには正式登録後のID、PASSWORDが必要です。
■この記事に関連したバックナンバー
●農業起業を成功させる視点と知的財産化する農作物の権利争い
●江戸時代の石高制度に学ぶ、市民農園を収益化する発想
●ヤワな日本人には太刀打ちできない一触即発の食糧危機
●成功者が究極の目標にするワイナリー経営のステイタス
●世界で拡大するベジタリアン市場と崩壊する日本の食文化
|
|
|
|